とな天短編小説『そこに優しさがあるから』
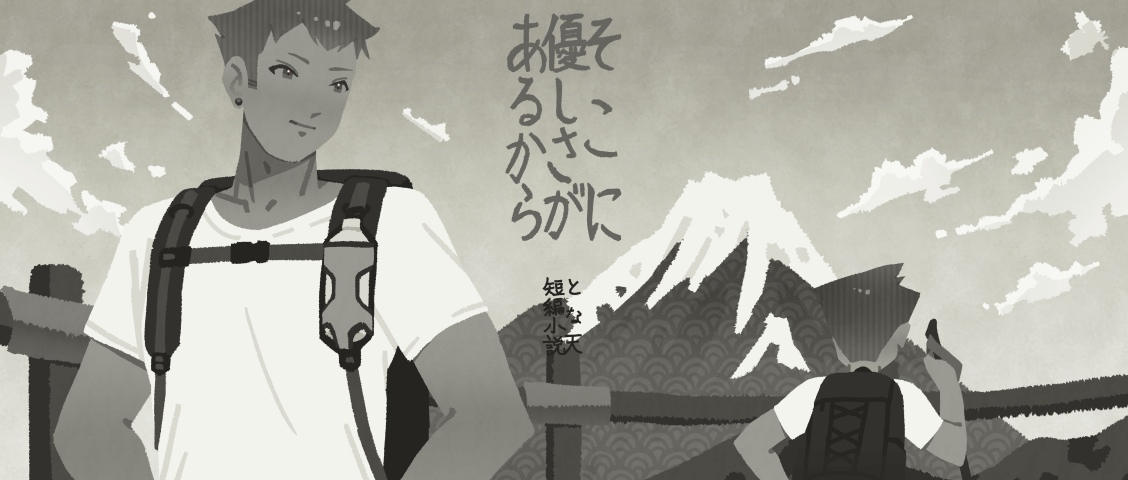
概要
- 拙作ゲーム『となりのクラスの知らないあの子は天使になったんだ』の短編小説です。
- 利田金星のお話です。
本編
老夫婦が振り返る。オレと目線が合わず、大きく上を向く。戸惑っている。二人とも春服を着込み、リュックを背負い、ハットを被っている。
オレは焼けた肌にTシャツ、真っ赤なズボン。ごつい、黒い、でかいリュック、背負えるだけの体格。眉間と鋭い目を広げて、明るい声で笑いかけた。
「撮りましょうか?」
夫婦が顔を見合わせる。オレはそっとデジカメを受け取る。
「ここだと標識と富士山が一緒に撮れますよ」
離れて立った夫婦に、「もーちょっと寄ってー」と声をかける。男性が女性の背中に手を回し、肘に触れ、肩を寄せ合う。
「撮りますよー。三、二、一」画面から結果が消える。「キレーに撮れましたよ!」
夫婦は丁寧に礼を言うと、広場の奥へ歩いて行った。
今日は登山日和だ。平日の頂上は案外混んでいる。昼飯を済ませたオレは頂上を後にした。
少し下りると、分かれ道に数人集まっていた。頂上への道を教えると顔が明るくなった。
また少し進んで、なくし物を探す人を見つけた。オレは頂上にあったタオルを思い出し、取って戻ってくる。驚かれたが、ほっとしていた。
感謝の言葉を聞いて、背を見送ると、オレはいつもうれしくなる。
山が好きだ。街を離れると空気が透き通って、時間がゆっくりになる。険しい山に挑むことも、こういう低山で人の存在を感じることも、全て山の魅力だ。
何より、山の優しさが好きだ。山を登る奴、守る奴、そいつらを助ける奴、皆の優しさで誰かが山を登れる。
角を曲がったとき、人の姿に目がとまった。母子がベンチに座り、父はしゃがんでいる。みんな軽装で、スポーツ経験者には見えない。細身で、特に子どもは中性的だ。
両親が子どもに笑いかけるが、子どもはうつむいたままだ。膝をすりむいている。
「こんにちは」親子に近づく。「どうかされましたか?」
両親が見上げる。父親が苦笑する。
「もう疲れちゃったみたいで。帰りたいらしいんですけど、もう頂上だし、どうしようかって」
「そりゃあ大変だ」膝を折る。「よければ治療させてもらえませんか。救急セットあるんで」
両親は一度ためらうが、「お願いしていいですか」と答えた。
オレはできるだけ低くしゃがみ、救急セットを取り出してから、子どもの顔をのぞき込む。子どもは半泣きでじっとオレを見た。
「足触るぜ」
声は無いが、目線は合っている。膝裏に手を添え、消毒液をかけると、足がこわばった。絆創膏を貼る。
「膝、痛いか」
目を見ると、子どもがうなずく。
「もう歩けない?」
大きくうなずく。
「でもなぁ、帰るのにも歩かなきゃなんねぇぞ」
「……おんぶしてもらう」
「それじゃ親が大変だろ」
苦笑いすると、子どもは口を結んでしまう。
「じゃあこうしよう。もうすぐそこが良い景色なんだ。せめてそこまで行こう」
首をふる。
「ちょっと歩くだけだぜ」
「歩けない」
「ここまで歩いてきたんだろ。帰るのも歩くんだ、少しくらい変わんねぇよ」
手を差し伸べる。子どもは鼻をすすり、拳を緩く広げ、オレの手のひらに置いた。手を引けば、よろけずに立ち上がる。
「ほら立てた」眉を上げて、得意げに口端を持ち上げる。「立てるんなら歩ける。行こうぜ」
子どもはぽかんとする。
両親に確認を取ってから、オレのストックを子どもに渡した。
「これが手前のもう一本の足だ」
ストックを握った子どもの手にオレの手を添えて、ストックの使い方を教える。オレが手を放せば、子どもは階段にストックを突いて、確かめながらぐっと登る。一つ一つ歩に進めて、次第にテンポが上がってくる。
たびたび声をかける。足の踏み出し方、疲れない道の選び方、教えればすぐ取り入れる。高い段差で手を差し伸べると、首を振ってひょいと登った。
開けた場所に出る。薄く晴れ渡る空に、濃い森色の富士山がどっしり構えていた。頂上に雪が被っている。柵へと踏み込めば、富士山の前に山と街が広がる。
子どもは柵をつかみ、ストックを握りしめた。その後ろから指を指す。丘の駐車場で車が光っている。
「あそこから歩いてきたんだぜ」
子どもは答えず、駐車場を見つめ、景色の隅々に視線を移す。
ふと、見下ろした子どもが昔の自分と重なって見えた。
記憶がよぎる。子どもの頃行った登山。おふくろをいたわる親父を横目に、妹と競争をしていた。調子よく登れけば妹の叫びも聞こえないほど遠ざかる。
足を踏み外した。膝一面すりむいて、踏み込む度にいたんだ。振り向いても誰もいない。急に心細くなった。
助けてくれたのは知らない大人だった。その人は手早く治療すると、オレにストックを貸し、見晴らしの良いところまで登らせてくれた。感動している間に家族も登ってきて、結局頂上まで登ってしまった。
オレはしゃがみ、「なあ」とつぶやく。子どもが振り向く。
「そのストック、お前にやるよ」
「でも」
「下りるのにもあった方がいいだろ」
改めてまっすぐ見つめる。子どもはすっきりした顔で見つめ返す。
「その代わり、約束だ。他の誰かが困ってたら、そのストックを貸してやれ。今じゃなくていい。いつか、そのストックを手放せるくらい強くなったら、貸せる人間になれ。できるか」
子どもが力強くうなずく。オレもうなずき返した。
両親に話を付けてから、オレたちはそれぞれの道へ進んだ。手を振ると、子どもは誰よりも大きく手を振って、大きい声で言う。
「お兄ちゃん、ありがとう!」
「おう!」
山を下る。木の影に沿って下り、そのうち木の天井ができて、暗くなる。すれ違う人に挨拶をすれば、明るい声や、疲れた声が返ってくる。
コンクリートの道になれば、すぐ駐車場だ。車を開けて靴を履き替える。運転席に座って、大きく息を吐いた。
また、山に登ろう。
